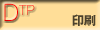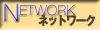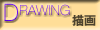2004年7月9日
ベルリン・フィル 12人のチェリスト
- クレンゲル 賛歌
- ハイドン バリトン・トリオより
- メンデルスゾーン エリアより
- バッハ フーガの技法より
- ヴィラ=ロボス ブラジル風バッハ第1番より
- バカラック サウス・アメリカン・ゲッタウェイ
- グレン・ミラー ムーンライト・セレナーデ
- 黒人霊歌 ディープ・リヴァー
- ガーシュウィン クラップ・ヨー・ハンズ
- マンシーニ ピンク・パンサーのテーマ
- カイザー=リンデマン ”12人”のためのボサ・ノヴァ
- ピアソラ アディオス・ノニーノ
- ピアソラ リベルタンゴ
- ピアソラ フーガと神秘
- ベルリン・フィル 12人のチェリスト
- 東京文化会館
まあ、盛りだくさんのプログラムで飽きさせない。この人たちのことは言うまでもないのだが、一つの楽器だけでまとまってアンサンブルできるのはチェロだけだね。
ファウストとクワンツが交代でリーダーになるのだが、それぞれの特徴がでていておもしろかった。ファウストはものすごいリーダーシップで、常に全員に気を配っている。クワンツは幅広い音色を持ち、さすがに首席だ。
誰がソロを弾いてもうまい、なんてオケは他にないだろうなあ。
2004年6月26日
イタリア・パドゥヴァ管
- モーツァルト フィガロの結婚序曲
- モーツァルト ピアノ協奏曲第9番
- ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番
- ピアノ・指揮:ウラディーミル・アシュケナージ
- イタリア・パドゥヴァ管弦楽団
- 東京文化会館
アシュケナージは初めて。割と期待して行ったんだけれども、オケは普通。アシュケナージはうまいんだけれどそれ以上じゃない。
確かにモーツァルトとベートーヴェンじゃあタッチも変えて、音色も変化をつけているのだが、何か表面的で、おもしろくない。
オケは室内オケとしては雑な響きで、これだったら大きなオケでアラが見えないほうがいいや、ってかんじ。
2004年6月9日
ハンナ・チャン チェロリサイタル
- リゲティ 無伴奏チェロ・ソナタ
- バッハ 無伴奏チェロ組曲第5番
- ブリテン 無伴奏チェロ組曲第1番
- 東京文化会館
以前、ドレスデン=シノポリと確かシューマンのコンチェルトを聴いたことがあるのだが、音が汚いというか、無理矢理音を出していて嫌い! と思っていた。
いやまったく。音の傾向は変わらない。リゲティは「2001年宇宙の旅」くらいしか知らないが、普通の曲。
バッハはどんなアレンジをしてもバッハに聞こえる、というのが持論だったが、生まれて初めてバッハに聞こえなかった。ただの音の羅列。それにしても最初のCの重音。下は開放弦だぜ。なぜ合わない。音程は悪いし、音は汚いし、気分が悪くなってきた。
というわけでブリテンは聞かずに帰ってきました。
2004年5月15日
ハイティンク指揮 ドレスデンシュターツカペレ
- モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」
- R.シュトラウス 英雄の生涯
- 指揮:ベルナルト・ハイティンク
- ドレスデンシュターツカペレ
- 東京文化会館
この日を待っていたのですが。
ドレスデンも普通のオーケストラになってしまった。
2004年4月19日
マズア指揮 フランス国立管弦楽団
- デュカ 魔法使いの弟子
- ハチャトリアン ヴァイオリン協奏曲
- ヴァイオリン:セルゲイ・ハチャトリアン
- ムソルグスキー 展覧会の絵
- 指揮:クルト・マズア
- フランス国立管弦楽団
- 東京文化会館
マズア=フランス国立管ということで、あまり期待していかなかったのですが。
魔法使いの弟子は、演奏していて難しい、という感が先立って、いつもあまり楽しめない。不幸だね。この日の演奏は、鈍くミッキーもノリが悪そうだった。
さて今日のメインイベント、といってもハチャトリアンというヴァイオリニストは全く知らず、当日のプログラムで19歳(!)ということを知ったわけです。ハチャトリアンが弾くハチャトリアンのコンチェルト、ですが、血縁関係はないそうです。
で、ヴェンゲーロフ以来の衝撃。思い起こせばヴェンゲーロフを初めて聞いたのも、彼が19歳、ライプツィヒでの事でした。ハチャトリアンの使用楽器はグァダニーニということですが、ストラドのように鳴らない代わりに、丁寧に、楽器の特性を最大限に引き出して鳴らしていた。テクニックの完璧性はいうまでもないのですが、それよりもストラドではない楽器であれほどの響きを出すことに驚きました。
ところで、最近はニセストラドが多いように思いませんか?
アンコールにイザイの無伴奏。これもまたヴェンゲーロフを思い出させてくれました。
最後に展覧会の絵。ラヴェルではなく、ゴルチャコフという人の編曲版でした。やっぱりどうしてもラヴェルを意識してしまうのだろうし、おもしろかったのは、パーカッションの人が、この版にはない、ラヴェル版のムチとかスネアなどが入る部分とカラ打ちしていたことでした。
マズアの演奏もゆとりがなく、テンポが速いのはいいんだけれども、展覧会場に16時30分に入って、駆け足で見てきました、という感じ。
編曲版としてはストコフスキーのものが一番雰囲気がでていると思っていますが、今日のはあまり説得力がなかった。
アンコールに「カラをつけた雛の踊り」と「ルスランとリュウドミーラ」。
2003年12月1日
メータ指揮 イスラエル・フィルハーモニー
- シューベルト 交響曲第6番
- マーラー 交響曲第6番
- 指揮:ズービン・メータ
- イスラエル・フィルハーモニー
- 東京文化会館
久々のイスラエル・フィル。また、あの美しい弦の音を聞かせてもらえると思うとわくわくです。
シューベルトはマーラーとの6番つながりで置いたのだろうと思うけれど、中途半端で意図がよく伝わらない。演奏も散漫。
マーラーは最近の研究で第2楽章と第3楽章を入れ替える、という案が出されていて、メータもそれに従うということだ。ただし、どのような意図なのかはっきりしない。元の通りの方がいいような気もするのだが。
オーケストラは以前聴いたように圧倒的な弦楽器とおまけの管楽器、というような構図ではなく、もちろん弦楽器は強力なのだが、非常にバランスの良い演奏だった。ただし、トランペットはいつもはずし気味。
メータのマーラーはちゃんと聴いたことがないけれど、意図があるのかないのかよくわからないが、あまり抵抗のない演奏。下手するとおもしろくなくなるのだが、さすがにオケの力というものはこういうもんだ。
2003年11月21日
フルネ指揮 チェコ・フィルハーモニー
- ピエルネ 「ラムンチョ」序曲
- ラヴェル ピアノ協奏曲
- ピアノ:伊藤恵
- ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
- フォーレ 「シャイロック」組曲
- ラヴェル ボレロ
- 指揮:ジャン・フルネ
- チェコ・フィルハーモニー
- 東京文化会館
フルネとチェコ・フィルという、相性がいいんだか、期待していいのかどうかわからない組み合わせでした。
ピエルネは難しいのでしょうか? リハーサル不足なのでしょうか? 細かいパッセージが弾けてない、合わない、とフルネさん許しちゃっていいの? という出来。
ピアノ協奏曲はオケのバランスが良かった。ピアノはもう少し鳴ってもいいのでは。
牧神の午後は、これこそフルネの真骨頂という感じで、おけもよく応えていたと思う。
シャイロックは僕が大好きな曲で、歌の部分がカットされていたのは残念だが、オケの響きが最も充実していた。チェコ・フィルの体質にも合っているのでしょうか?
ボレロは何でチェコ・フィルがこんなくだらない曲をやるの? というぼやきはさておき、なかなかすばらしい個人技を見せていた。これはボレロに限らないのだが、楽器間のつながりが悪いというか、後から入ってくる方が少し遅い。これはチェコ・フィルの伝統なのか? しかし、これは独特のひなびた響きにあったスタイルなのかも。
2003年11月7日
北とぴあ国際音楽祭記念事業 オペラ≪イポリートとアリシ≫
- ラモー オペラ≪イポリートとアリシ≫
- 指揮:寺神戸亮
- レ・ボレアード
- 北とぴあ・さくらホール
ラモー50歳にしての処女オペラ「イポリートとアリシ」は主に上演の都合による改訂や削除がおこなわれてきたが、コンサート形式ながら全5幕、初演のあるべき姿で日本初演となった。
1994年の第1回北とぴあ国際音楽祭から数えると結成10年にもなる「レ・ボレアード」は、いきいきとした音楽を聴かせていた。指揮の寺神戸はラ・プティット・バンド、バッハ・コレギウム・ジャパンのコンサートマスターを務めるバロックヴァイオリンの名手であるが、1995年の北とぴあ国際音楽祭において指揮者デビューを飾った。オーケストラは日本の古楽界をリードするメンバーで固められ、時にロマン派の音楽ではないかと思わせるほどの転調する場面でも安定した演奏をしていた。また、様々な効果音(風、波など)を演出するために管楽器のメンバーが時にパーカッションを担当するなど大活躍だった。合唱団は各パート3人ずつで構成され、合唱だけでなく、登場人物の多いこのオペラをカバーするため、それぞれソロも歌った。
フランス語のオペラでは言葉、語感、発音が気になるが、ソリストにジャン=フランソワ・ノヴェリ、ガメル・メシャリー、ステファン・マクラウドというフランス語圏一級の人たちのほか、エコール・ノルマルへ留学の経験がある野々下由香里、歌詞に対して深い理解を示す波多野睦美を揃え、質の高い上演となった。
(カンパネラNo.22に掲載)
2003年9月29日
ヴァンスカ指揮 フィンランド・ラハティ交響楽団
- シベリウス 序曲「カレリア」
- シベリウス ヴァイオリン協奏曲
- ヴァイオリン:ギャレット
- シベリウス 交響曲第2番
- 指揮:オスモ・ヴァンスカ
- ラハティ交響楽団
- サントリーホール
1999年にシベリウスチクルスで感銘を与えたラハティ交響楽団が再来日した。今回もシベリウスプロをひっさげての登場だが「フィール・フィンランド」というフィンランド文化を紹介する催しの一環として全国各地で演奏された。初日のサントリーホールでの演奏に先立ち、コンサートの前にラハティ市の主催によるカクテル・セミナーが開催された。セミナーではフィンランド政府観光局局長の挨拶の後、ラハティ響総責任者、フィンランド・トラベル社のマネージャーによって、オーケストラやラハティ市についての説明が行われた。
それにしても人口11万人の都市にこのようなすばらしいオーケストラが存在することがうらやましい。プログラムは序曲「カレリア」、ヴァイオリン協奏曲、交響曲第2番、そして第2の国歌といわれる「フィンランディア」という最もポピュラーなもの。演奏はどこをとっても立派だが、聞き手が期待するシベリウスの寒さだとか、ほっとする暖かさに欠けでいる。ヴァイオリンのギャレットは1980年生まれ、テクニックもルックスも人気がでそうな逸材。大成して欲しい。
(カンパネラNo.21に掲載)
2002年11月25日
ゲルギエフ指揮 キーロフ歌劇場管弦楽団
- プロコフィエフ 交響曲第1番「古典交響曲」
- プロコフィエフ ピアノ協奏曲第2番
- ピアノ:アレクサンドル・トラーゼ
- プロコフィエフ 交響曲第3番
- 指揮:ワレリー・ゲルギエフ
- キーロフ歌劇場管弦楽団
- 東京文化会館
オール・プロコフィエフという、何とも出かける気のしないプログラムだったが、これはすごかった。
「古典」はどうしたって難しい曲。ごまかしが利かないのだが、ごまかした演奏しか聴いたことがない。ところがこのオーケストラはまったくごまかそうとしない。弦楽器がプレスをしない奏法のため、響きが透明になるのだが、その分少しでも合わないと目立つ。5−4.5−4.5−3−2.5くらい? の編成。完璧とは言わないまでも大変に純度の高い演奏だった。
ピアノコンチェルトは学生時代の作品で、革命の最中に楽譜が紛失し、後にプロコ自身が記憶を元に書き直したそうだ。ソリストのトラーゼはまったく知らない人だが、こんなにピアノを鳴らす人は聴いたことがない。しかもあの上野のスタインウェイだ。ミスタッチが全くないわけではないが、そうとうな難曲(かなりでたらめと言ってもいい)を見事に弾きこなしていた。
オケの伴奏も見事で、第1楽章の最初の部分で、ピアノがアルペジオを弾いていてオーボエが旋律を吹いているのだが、ピアノのルバートにオーボエが完璧に合っていた。バランスもよく、オケが曲を理解しているのがよくわかる。
シンフォニーはオペラの改作らしいが、どこをとっても背景描写で、主人公がいつまでたってもでてこない、という感じ。曲はへんてこだが、演奏の質は高く、音の響きだけで満足できた。
セコバイトビオラに一人プルトがあるのはなぜなんだろう。
2002年10月28日
ブーレーズ指揮 ロンドン交響楽団
- ブーレーズ 弦楽の本
- シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲
- ヴァイオリン:クリスティアン・テツラフ
- マーラー 交響曲第5番
- 指揮:ピエール・ブーレーズ
- ロンドン交響楽団
- 東京文化会館
ブーレーズです。それにしても長い演奏会だった。
最初は自作の弦楽の本。演奏直前に何か音程のあるノイズが聞こえる。あらら、と思っているとブーレーズは引っ込んでしまった。しばらくして音は消え、再登場。それにしてもすべてを音で表現しようとするのだろうか? 盛り上がりはするが起伏にかけるのでは?
テツラフはテレビで見たことがあるだけで、そのときは汚い音だなあ、と思ったけれど実際には美しさの極致といった感じ。ストラドの官能性ではないけれど、すべてが磨き抜かれている。シマノフスキは相当の難曲だが、全編おとぎ話というような曲。
以前からブーレーズの音は明るいなあ、深刻なところがないなあと思っていた。「感情を廃し、徹底的にスコアに忠実な演奏」なのだと言われてもそれで納得するわけにはいかない。マーラーの5番でもやはり明るい。一つにはブーレーズがオケをよく鳴らすためでもあるだろう。
決して完璧な演奏ではなく、傷も多々あり、音程も不安定な部分があった。ふつうなら「けっ」というところなのだが、不思議な満足感がある。何かはよくわからない。今後の課題です。
オケはブーレーズの指揮で緊張していたのか?
2002年10月10日
飯守泰次郎指揮 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
- ブルックナー 交響曲第5番
- 指揮:飯守泰次郎
- 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
- 東京文化会館
飯守=シティー・フィルは集中的に作曲家シリーズを行っている。ベートーヴェンから始まり、ハイドン・ブラームス、ブルックナー・メンデルスゾーン、と数少ない定期演奏会でオケの水準を高めていくにはとてもよいことだと思う。
シティー・フィルは以前は単に勢いだけで演奏しているようなところがあったが、最近は自信を持って演奏している。これが音楽的な確信を持てるようになるとすごいのだが。
さて、ブルックナー、5番。弦は18型、木管はノーマルだが、金管は倍管にしている。飯守さんによればヨーロッパではよくある形らしいが、飯守さん一流の悪趣味の一つに思えた。結局テュッティで吹くのは最後の最後だけ。ここまで待って、完璧なハーモニーを聞かせられるのなら大成功。あるいはもっと響きのあるホールでなら効果があったのだろうが、上野では苦しい。また、飯守さんは力の抜けた、余裕のあるヨーロッパスタイルのふくよかな音を求めたのだろうが、奏法としても問題があったかも。
全体的にはとても立派な演奏でした。だけれども、これがベートーヴェンなら満足していたと思う。ブルックナーってモノトーンに思えるけれども、いろんな表情、音色が必要だ。ピッツィカートの伴奏の上でファーストヴァイオリンが寂れた音色で切々と語っていたかと思うと、次の瞬間にはオルガンのフルトーンの華やかさが来る。これを単にボリュームの違いだけでやっていてはとてもつまらない。
本当に美しい(と思わせる、あるいは思いこむ)音、瞬間的に爆発する音、わびさびを感じさせる音。いろんな引き出しが必要だ。「もっと美しい音がほしい」と言ったら、それを聞いていた人に「ぼくは十分に美しいと思う」と言われたが、そういう意味ではなく、様々な音色の使い分けと、お客に「ここはこんなに美しい音なんだ」と(実際にでている音はともかく)信じさせることができたら、と思う。
木管は核になる人が必要なのかな。とりあえず音を出している、という感じ。自信を持つこと。みんなで寄り添って音楽を作っていくこと。例えばオーボエなんか、アメリカのオケのいわゆるアメリカン・ドルチェなんて必要ないと思う。オーボエ本来が持つ素朴な音でいいから、音楽的確信を持って演奏してほしい。
とはいえ、シティー・フィルがこんな演奏をしているなんて世間的には知られていないのだろうけれど、これで財政が安定し、定期演奏会が増えてくればすごいことになると思うが、そうなると他のオケと同じになってしまうかも。
2002年9月29日 リー・シンサオ指揮 中国国家交響楽団
- シュー・ツェンミン 交響詩「楓橋夜泊」
- ハチャトリアン ヴァイオリン協奏曲ニ短調
- ヴァイオリン:リー・チャンユン
- ラフマニノフ 交響曲第2番
- 指揮:リー・シンサオ
- 中国国家交響楽団
- 東京オペラシティー
これはすごいオーケストラだ。北京中央楽団を改組して、中国最高のオーケストラを作ったと、話には聞いていたが、本当だった。
オーケストラの演奏会はチューニングで始まるが、これでオーケストラのキャラクターがわかる。ピッチはそんなに正確に合わせないけれど、よい音色で、自信たっぷりの音を出している。
「楓橋夜泊」はとても面白い、という人もいたが、ぼくには出来損ないのラヴェルのような気がして楽しめなかった。木管のピッチが会わない場面もあったけれど、とてもよい音色で、堂々とした演奏だ。
ヴァイオリン協奏曲はハチャトリアンという珍しい曲だが、リー・チャンユンという熊のような若者が見事に弾ききった。音はまったくジュリアードでぼくの好みではないが、とにかくどんどん突き進む。圧倒的なテクニックで大ブラボーをうけていた。オーケストラもまったく見事。アンコールにバッハの無伴奏ソナタ第1番のアダージオ。約半世紀前のスタイルだ。もう1曲、モンティのチャールダッシュ。これはギネスに挑戦、の演奏で、ラカトシュよりも早かった。
ラフマニノフはよく理解されているのだろう。まったく破綻のないどころか、全員がわかって、確信を持って演奏していた。オーケストラとしてはぼくの好みではない。つまり、どのパートも大音量を目指し、アメリカというか、ロシアのスタイルなのだろうけれど、音楽的知性に欠けるような気がする。今や、オケのバランスだってプレイヤーが自発的に調整するものだ。特にここの指揮者は音楽の表面をなぞるのが好きで、音楽の骨格や構造にはあまり興味がないみたいだから、時折バランスが悪かったり、構造として重要な内声のリズムがふらつく場面もあった。
アンコールは有名な曲らしい弦楽合奏の中国の曲。みんなが曲をコントロールしているようで、とてもすてきだった。もう1曲、外山のラプソディー。「やられたっ」と思いました。
2002年9月25日
矢崎彦太郎指揮 バンコク交響楽団
- ナロングリット・ダーマブトラ 「シンフォニア・チャクリ」
- ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調
- ピアノ:イントゥアン・シカラノン
- ストラヴィンスキー 「火の鳥」(1945年版)
- 指揮:矢崎彦太郎
- バンコク交響楽団
- 東京オペラシティー
「アジア・オーケストラ・ウィーク」という企画があり、タイ(バンコク交響楽団)、フィリピン(フィリピン・フィルハーモニック管弦楽団)、オーストラリア(クイーンズランド管弦楽団)(これはアジア?)、中国(中国国家交響楽団)、韓国(プチョン・フィルハーモニック管弦楽団)の5団体が参加して、オペラシティーで演奏された。
初日のバンコク響は日本人の矢崎彦太郎が2000年より名誉指揮者をつとめているという。タイでの音楽(ヨーロッパ音楽)環境はどうなのかまったく知らないのだけれど、パンフレットによるとバンコク響は創立20周年を迎えた、ということだ。まあまあきちんと弾いているが、それ以上のものはなく、「何かを表現する」ということは重要ではないようだ。
このシリーズでは毎回自国の作曲家の作品が置かれている。ダーマブトラは1962年生まれ。タイ音楽を知らないので民族音楽が用いられているかどうかはわからないが、タイの王族は作曲をよくするらしく、王様の曲を引用しているという。
ピアノ協奏曲は最初のムチが不発だったように感じたのだが、もう一度でてくるときも同じだったので刺激的な音は好みではないのだろう。ピアニストは器用に弾くけれども、楽器を鳴らすという考えはないようだ。スタインウェイのフルコンサートがアップライトのような音を出していた。ピアノに限らず、オーケストラも器用に弾いているが、楽器が鳴っていない。弦楽器は明らかにひどい楽器であるが、その楽器の性能を最大限に引き出せばオーケストラとしてそうとうな音になるのだが。
続くストラヴィンスキーもそうだが、指揮者の趣味を出したようであるが、このオーケストラの魅力を出す選曲とは思えない。せっかく日本に来て、よいホールで演奏するのだから、本当に魅力を引き出せる選曲をしてほしかった。
アンコールは今の王様が作曲したらしい、かわいらしい曲。
面白いのは、ヴァイオリン、ヴィオラの弾き方がまったく同じ、右手の形、ボウイングが同じ形なのだ。教師が一人しかいないのだなあ。
2002年9月4日
リッカルド・ムーティ指揮 スカラ・フィルハーモニー管弦楽団
- ロッシーニ 歌劇「ランスへの旅」序曲
- ハイドン 交響曲第104番
- ベートーヴェン 交響曲第3番
- 指揮:リッカルド・ムーティ
- スカラ・フィルハーモニー管弦楽団
- 東京文化会館
スカラ・フィルというのはウィーン・フィルみたいなものなのかねえ。「スカラ座を母体とした、まったく独立した形」というのは。
残念ながらロッシーニの序曲を聴くことができませんでした。電車時間の見積もりを間違えたためです。
ハイドンは14型という大編成。以前、ラジオで聞いたムーティ=ウィーン・フィルのモーツァルトの印象だとムーティというのはすっきりした古典の演奏を好むのかと思っていたが、ブラームスのセレナーデあたりを聞いたような気分。オーケストラは第一級だから、演奏に不満はないし、とにかく全員がよく歌う。しかし、どうしてもハイドンを聴いた気にはならない。
エロイカはますます人数が増えて、16型でなんと倍管。ホルンにもアシがついた。とにかく立派な演奏。第2楽章のコントラバスなんて、あんな音楽的な演奏は聴いたことがない。しかし、どうしてこんな時代錯誤なことをするのだろう。今、小編成ですっきりとしたやり方がはやっているからわざと逆をやっているのだろうか。演奏は立派だけれども、ベートーヴェンはどこに行った? という感じ。大編成の常として、各声部が埋もれてしまうことがある。第1楽章でも、低弦がテーマを弾いていて、ファーストヴァイオリンとセカンドヴァイオリンが交互にシンコペーションとフィギュアを弾くところがあるが、どちらかというとシンコペーションは脇役なのにどうしても強く聞こえてしまう。小編成だとこのあたりは難なく解決できるのに。
ところで20年ほど前から「今、エロイカを演奏する意味はどこにあるのか?」と感じています。ベートーヴェンの交響曲というのはある普遍性を持っていて、時代や場所を超越しています。その中で3番はぼくにはある意味ローカルな、つまり、時代と場所がしっかり限定されている感じがするのです。まあ、この話は自分でもまだ決着が付いていないので、また改めて書くことにします。
というわけで大ロマンチックなエロイカを聞いた後、アンコールは「運命の力」序曲。まさにこれを聞きに来たのでした。もう、最初からオケの音がまったく違う。スカラのシルクのような肌触りの音色がようやく聞くことができました。これは単に慣れている、という話ではなく、彼らの身体の一部であり、生活の一部であり、必需品なのだ。まさに奴らにとっての邦人。聞いていて涙をこらえるのに必死でした。
2002年5月23日
飯守泰次郎指揮 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
- シューベルト 交響曲第5番
- ブルックナー 交響曲第4番
- 指揮:飯守泰次郎
- 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
- 東京文化会館
飯守さんの大得意技大会。
シューベルトはいい曲だね。でも冒頭の木管は合っていて欲しいし、弦楽器も「本当に」よい音で弾いて欲しい。シティに限らず、日本のオケは個人の技量がオケの技量につながらない部分がある。一人一人はいい音を出しているのに、オケとなるとまとまらない。やはり日本のクラシック音楽はヴァイオリンが中心であったためか。根底にコントラバスがあり、その倍音に全員が乗る、という構造を日本のオケで聞いてみたいものだ。さらに高弦と低弦の接着剤であるヴィオラ文化もまだ育っていない。ヴィオラの音自体は結構よくなっているのに、オケをコントロールする肝になっていないのだ。
それはともかく、シティはようやく「オケの音」が出始めたばかりなのだ。一つの倍音に集約しつつある。ところが今回のブルックナーは音を出すことにこだわりすぎたのか、音量は出るが音が集まらない、という結果になってしまった。ひょっとして最近の演奏が「音が出てきたから集まってきた」と勘違いしていないか? 「音が集まってきたから音が出てきた」のであって、無理に出すと(今回の演奏)壊れていってしまう。
せっかくブルックナーという素材だったのだから、無理な音出しをしないで、オルガントーンに身を委ねればよかったのに。出だしのホルンは緊張していたが立派。「もっと何とかならないのか」という人もいたが問題ない。
ところで、飯守さんは珍しくグロッケンを使わなかった。まあ、使う方がおかしいのだが、飯守さんが使わなかったのは珍しいことだったのだ。
2002年5月18日
マレイ・ペライア&アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールド
- ヘンデル 歌劇「アルチーナ」より組曲
- モーツァルト ピアノ協奏曲第21番
- J.S.バッハ ピアノ協奏曲第1番
- モーツァルト 交響曲第41番
- 指揮・ピアノ:マレイ・ペライア
- アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールド
- 東京文化会館
昔はアカデミー室内管弦楽団だったのが今はちゃんとした名前になった。以前、マリナーで聞いたことがあるが、マリナーの何とも落ち着きのない棒に感心しなかった記憶がある。
一曲目はヘンデルの歌劇を組曲にアレンジしたもの。棒なしで演奏されたが、曲が冗長で平板なのが残念。演奏スタイルはもはやモダン奏者が好みを言っていられる時代ではなく、じゃなくて、ここはいち早くバロック奏法を取り入れたはずだが、1980年代あたりで進化が止まっている感じ。ビブラートを抑制し、リズムを強調するやり方はいかにもだが、もはや様式化してしまっておもしろみがない。細かいリズムが合っていなかったのは×。やはり寄せ集め楽団の限界か。
モーツァルトでいよいよペライア登場。ぼくはまったく知らない人であり、興味もなければアカデミーの首席客演指揮者であることすら知らなかった。
いやー、実に澄んだ音で粒も揃い、久しぶりにいいピアノ聞かせてくれました。オケもさすがに得意のモーツァルトで、文句なし。
バッハはペライアがとても好きなことはわかるんだけれども、現代においてどう決着を付けたいのか。結局その悩みが解決されず中途半端な印象。まずピアノを使うこと自体は奏者の勝手だからよいとして、それをチェンバロ的に演奏するのか、ピアノ的に演奏するのか、ペライアはどっちともつかない。第一楽章はチェンバロ的にしようとして軽いタッチだった。しかし、第三楽章になってくるとどうも気持ちが高ぶってくるためか、ピアニスティックになり、それと共に音楽もロマンティックになってくる。
ジュピターはどうしたらいいんだろう。これもまたぼくが納得できるものを聴いたことがない曲の一つだ。もっと弦楽器の音色がよければ。もっとアンサンブルがよければ。もっと。。。でも、この曲はどうしたって神とロマンに挟まれた古典なのだから、どうしようもないのかもしれない。
2002年2月26日
マリス・ヤンソンス指揮 ピッツバーグ交響楽団
- ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲第1番
- ヴァイオリン:五嶋みどり
- ブラームス 交響曲第1番
- 指揮:マリス・ヤンソンス
- ピッツバーグ交響楽団
- 東京文化会館
ショスタコのヴァイオリン協奏曲は恥ずかしながら知りませんでした(もともとコンチェルトはあまり知らないので)。ついでに五嶋みどりも初めて。
第1楽章。暗い雰囲気で曲が進む。みどりは悪霊にでも憑かれたかのような動きだ。音はしっかりしていて、芯があるのだけれどもどこか浮遊する感覚がある。あ、これはシェーファーの時に同じことを感じた。動きが目障りなので視線を逸らして聞いてみるが、そんなことで印象が変わるはずがない。
ところが第2楽章。スケルツォ。まったくこの空間を支配してしまった。さっきまで何か他に気にかかることがあるような感じの音だったのが、一変した。おなじみのD-Es-C-Hも聞こえてくる。
第3楽章もぼくが知っているショスタコだ。静かな中に決然とした感じがあり、アイロニカルであっても優美さがある。訳のわからないことを言っているけれど、いろんな感情が織り込まれているのだ。みどりは一点の曇りのない音で、こうした感情を表現していくが、楽章の最後におかれた長いカデンツァには本当に驚いた。みどりはものすごい集中力で弾ききるのだ。
そのまま第4楽章にはいる。人間ってこんなことができるんだ。唖然。
オケも木管がちょっと鈍いかな、くらいで、高い集中力でサポートしていた。
さて、ブラ1。16型、倍管。最近ではとても珍しい。ラッパとトロンボーンは山台に乗らず、しかも斜め向きだ。始まりはとても厚い音だが淡々と進む。ひたすら淡々と進む。アレグロ。ちょっと速く入りすぎたのか、ブレーキがかかる。あららと思っていたらそのテンポになった。うーむ、設定ミスか。しかし、いつでもどこでも厚い音でなっていて(この編成だと当たり前)、翳りとか、憂いとか、ブラームスにつきものの感情が全くない。楽譜に音があるからならしている、という感じ。
第2楽章も同じように進む。やがてソロ。ヴァイオリンはちょっとせっかちでリズムもあっさりとるのでホルン、オーボエとちと合わず。しかし、そのあと、クラとフルートが盛大に伴奏するのはなぜ。バランスをとることを知らないのか?
だんだん飽きてきたが、ここでちょっとした事件が起こった。ぼくは客席でどんな音が出ても気にならない(たとえ携帯が鳴っても。実際に経験有り)のだが、舞台上での雑音は許せない。「ひゅっ」っという音が聞こえたときは最初わからず、指揮者が興奮しているのかと思ったが、オーボエのお姉ちゃんがキーのつばを吹き飛ばしていたのだ。何しろアシがついているので、ソロを吹くだけでテュッティやロングトーンはお休みだからその間盛大に吹き飛ばしているのだ。しまいには管を抜いて掃除を始めたり。「ソロがうまくいかないのは私のせいじゃないのよ」とでもいいたいのか?
第4楽章。ここの序奏部で、ピッチカートが終わったあとヴァイオリンが掛け合いで16分音符を弾くのだが、f→p→fと遷移していくときどれだけpにできるかがぼくのキーポイントだ。pになればなるほど緊張感が増し、爆発もする。ところがやはり音符を弾いているだけなのだ。がっかり。
ブラームスはまったくさまにならなく、終わると同時に席をあとにしてしまったが、オケの素性はそんなに悪いとは思わない。弦は洗練されていないが、音はしっかりと出ていてしかも無理矢理出している音ではない。金管も離れて座ってはいるがオケをつぶすような音を出すわけでなく、立派。ホルンがちょっとコントロールミスがあったか。
まあ、ブラームスとは相性が悪かった、ということか。
2002年2月21日
飯守泰次郎指揮 東京シティ・フィル
- チャイコフスキー スラブ行進曲
- チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲
- チャイコフスキー 交響曲第5番
- チェロ:藤原 真理
- 指揮:飯守 泰次郎
- 東京シティーフィル
- 東京芸術劇場
なんと! チャイコプロですが、チケットをいただき、聞いて参りました。すごいことが起きたのでした。
都民芸術フェスティバルの一環で、低料金で東京のオーケストラを聴こうというシリーズです。15年くらい前はこの企画を利用して、その年の定期会員になるオケを決めていました。
というわけでシティーフィルとしてはまれにみる客入り。普段の倍は入っているじゃないかな。
一緒にいった人が「1812年だと思っていた」と騒いでいましたが、まあ、どっちだって同じような曲です。でも、ヴィオラの一番後ろで弾いているお姉ちゃんがとても張り切って弾いているので気持ちがよい。
ロココで感じたのだが、チャイコってかなりロマン派だと思うのだけれど(つまりファンタジーの要素が強く、気分的であるということ)、飯守さんは何らかの様式を作ろうとしているように感じた。出だしはもっとレガートでいいのでは、と思うのだけれども、単にファンタジーにはしたくないということか?
真理さんは遙か昔にドボコンを聞いたことがあるきりで、そのときはオケに完全に負けていて「音量のない人」というイメージがあった。しかし、今日は音がとてもよく通り、まったく問題ない。もちろん大音量で圧倒するタイプではない。やはり室内楽で最大のパフォーマンスを発揮する人か。アンコールにバッハ無伴奏1番のプレリュード。今時珍しいロマン派の演奏。
さてシンフォニー。今日はヴィオラが大変充実していて、時にチェロを圧倒するくらい。しかし、ヴァイオリンがいつものように安い音。ピッチさえ合っていりゃいいってもんじゃない。第1楽章は飯守さんが細かいテンポチェンジをして、シティーフィルじゃないとついていけないかも、って思った。しかし、完全にインテンポに落ち着くまで若干の時間がかかる。第2楽章は弦楽器がしっかりと背景を作り上げたところに情けないホルン。チャイ5のソロを吹くのならもっと覚悟しないと。第3楽章は早いところは落ち着きがなかったか。
そして第4楽章。十分時間をとってから始まる。それにしてもチャイコフスキーはなぜあの調にしたのだろう。ヴァイオリンの音がないところはいつも違和感を感じるのですが。アレグロに入って突然飯守さんが荒れ狂い始めました。こんなテンポではない、もっと激しく、と言っているようです。オケがどうしても落ち着くところへ行ってしまうのをわざと邪魔をしているようです。オケも困惑しているようで、あたふたしたまま音楽が進み、飯守さんはますます暴れまくります。
ついに、コーダ。いったん切ったあと、おもむろに手を広げる(切ると同時じゃない、スマートじゃないところが飯守さんらしい)。そしてその瞬間、シティーフィルはオーケストラになったのでした。オーケストラとは構築物であり、構造体であります。全員がそれを組み上げ、そしてその中にいれば音をはずそうが何をやってもびくともしません。なぜこの瞬間にシティーフィルがそうなったのかわかりません。ヴァイオリンが安い音ではなくなった。ピッチはかなり狂ってきているが一つの倍音の中にいる。ホルンは相変わらずひどいがそんなことは気にならない。オーケストラの音量が2〜3dbくらい上がったような気がします。
アンコール(胡桃割り?)でもそれが持続します。もちろんシティーフィルはバレエに慣れているのでお手の物ですが、やはり一つの倍音の中にオケがいるのって特別なことだと思う。シンフォニーのコーダの記憶がそのまま続いています。
この体験がシティーフィルを変えてくれることを期待します。まだまだ問題の多いオケです。管楽器は情けないし、何より自信を持って演奏して欲しい。しかし方向が見えたのじゃないでしょうか? 同じ方向をみていればますます倍音が増えるはず。
2002年2月15日
武蔵野合唱団37回定期演奏会
- ハイドン オラトリオ「天地創造」
- ソプラノ:鈴木 美登里
- テノール:櫻田 亮
- バリトン:青戸 知
- バス:高橋 啓三
- 指揮:本名 徹次
- 合唱:武蔵野合唱団
- 東京シティーフィル
- 東京芸術劇場
最近、ピリオド奏法を取り入れている本名さんがハイドンの大作「天地創造」を振るというので招待券を手配していただきました。
少し前に、本名さん本人に「モダンオケでピリオド的に演奏する場合、どのような指示を出すのか?」と質問をしました。100万円を要求されましたが、納得のゆく答えを聞くことができました。では、シティーフィルで実現できるのか? が今日の最大の関心。
これはもう、出だしから大成功。単にビブラートを止める(止められない人も数人いたが)だけであのような響きになるとは。あ、ビブラートだけでなく、音も短めにするなど、いろいろ工夫されていました。どのくらいの練習時間があったのか知りませんが、そう多くないだろうと思われる中でこれだけのことをやってのけたのは、本名さん本物です。
チェロのトップの人など(レチタティーボがあるせいなのか)バロックボウを使用する張り切りよう。音程がゆがむこともあったが、これは弓を使い慣れていないせいでしょう。モダンとは違い、軽い弓使いができれば問題がないはずです。
ビブラートを減じることで、音程の精度が問われることになりますが、おおむね良好でした。しかし、ベースは6本もあり、もう少し精度を上げる必要があるでしょう。きちんと合えば3本ですみます。
また、シティーフィルの輝かしくない音色が今日はプラスに作用し、落ち着いた響きになっていました。しかし、木管は本名さんのやろうとしていることをちゃんと考えるべき。自分の常識だけでしか演奏のできない人、他の可能性に興味を持てない人はプロとして演奏すべきではない。
歌はソプラノが特筆すべき。声量はないが、音楽がすばらしい。しかし、なぜ、ソリストを前に出さなかったのか? オケの前に来ればもっとよく聞こえたと思う。バスはぶつ切れの念仏。合唱は思いの外がんばっていた。
2002年2月1日
クリスティーネ・シェーファー・ソプラノリサイタル
- シューベルト
- 恋人のそばに
- ナイチンゲールに寄す
- 妹の挨拶
- 秋の夜の月に寄す
- 盲目の少年
- アン・ライルの歌
- 湖上の美人
- ドビュッシー
- 白夜
- 水彩画I「緑」
- 噴水
- ヴォルフ
- メーリケ歌曲集
- 東京文化会館
シェーファーという人は知らなかったので、行こうかどうか迷ったけれど、知り合いに「有名だよ」と言われて、聞いてみました。偶然取りためていたヴィデオがあって、グラインドボーンでやった「ルル」を見ました。美声ではないけれど、知的な(ルルとしてはいいのか?)感じのソプラノ、という印象でした。
シューベルトはいきなり立派な声で、少々ドラマティックすぎるかな? という印象です。どうしてもシューベルトは大ホールではなく、家庭とか、まあ、広い部屋、というイメージがありすぎるのかな。難しいところですね。ホール、しかも上野のような大ホールでシューベルトを歌え、という方が無理がある。
立派なシューベルトでしたが、何か足りない。立派なのにちょっとふわふわしている、何とも言えない感覚がありました。うまく言えないけれど。
フランス語の歌曲は、もうフランス語と言うだけで好きです。フランス語はまったくわかりませんが。例えばラロのようなつまらない作曲家でも歌曲となるととてもいい。そういう意味でドビュッシーはとても期待が高まりました。曲はドビュッシーの難しい面がちょっと顔をのぞかせていて、興味深かったけれど、フランス語に聞こえないんだなあ。フランス語独特のフッと、空中に舞う感じ、それがドイツ語のように自分の意味を考えたあとに相手に迫ってくる、という感じになってしまっています。
で、やっぱりヴォルフには当然期待が高まります。奇才ヴォルフにはいろんなタイプの曲がありますが、いわゆるキャバレーソングみたいのは心底好きです。今日はまじめな曲。メーリケの詩による歌曲です。
やっぱり立派なんだけどなあ。場所が悪いのか、うーむ。
この人の声はいわゆる美声ではないけれど、とても落ち着くし暖かい。技術が安定している。あとは神がかるだけか? 贅沢を言えば100人程度の会場で聞いてみたい。
ピアノはちょっと薄っぺら。
2001年12月13日
阪 哲朗指揮 東京シティーフィル
- 斉木由美 ことばの雫
- チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲
- ヴァイオリン イリヤ・グリンゴルツ
- ベルリーズ 劇的交響曲「ロミオとジュリエット」抜粋
- 指揮:阪 哲朗
- 東京シティーフィル
- 東京文化会館
チケットをいただいて閑散とした東京文化会館に行って来ました。
斉木さんは1964年生まれということですから、30代後半の若手作曲家なのでしょうが、経歴はまったく知りません。
もっと新しい表現方法があるのじゃないですか? 先人が試行錯誤したことをなぞっても意味がないじゃないですか。手法やモチーフを外に求めざるを得ないというのは、自分の中に表現したいものがないということになるのでは?
ヴァイオリンのグリンゴルツは19才(!)で、初来日らしいです。パールマンの弟子ということです。すばらしい音色と完璧なテクニック。オケのピッチが不安定になってしまうところもあったが、そんなものはものともしない。しかし、チャイコフスキーはなかなかに複雑で気まぐれなところがある。所々に表現がぶっきらぼうになるのは、どう処理していいのか考えあぐねている、ということなのだろうか? こうした場合、何が何でも自分の表現を作ってしまおう、というタイプと、素直に白状してしまうタイプがいるのだろうか? きっと解決してくれるに違いない。
第1楽章の序奏部はアーティキュレーションを際だたせるような演奏。これは今の流行を取り入れたものか? しかし、チャイコフスキーには通用しない。それにソリストのスタイルが違う。結局ここの部分だけが「ヘン」ということになってしまった。思いつきで演奏することはやめて欲しい。それからフィナーレのソロをかき消すラッパも考えなおさなきゃ。
ベルリオーズは、ふつうの感覚の人が演奏してもまったくおもしろくない。相当異常な人だったはずで、だからパガニーニなんかも興味を持ったわけでしょう。無意味とも思われる楽器編成。タンバリンとトライアングルが2人ずついる、なんて誰が思いつくでしょう。そして大編成にもかかわらず、テクスチャーがよくわかるうすい音響。それに対比するのはマーラーのような大音響ではなく、大狂乱。
というのを期待していて、ふつうの感覚で演奏されるとちょっとがっかり。出だしは弦楽器の他愛もないフレーズで始まるのだが、コントラバスのピッチカートがアクセントになる。もっとロマンチックな音が欲しいのだが、愛想のないピッチカートでがっかり。
終曲になってようやく指揮者も目覚めてきたのかな? という感じだが、意味のない指示、身振りが気になった。
ヴァイオリンの音色はもっともっと磨いて欲しいし、木管は悔い改めよ。テュッティのffで音が荒れてしまうのもなんだなあ。
2001年11月26日
ダニエル・ハーディング指揮 ドイツ・カンマーフィル・ブレーメン
- ベートーヴェン 「プロメテウスの創造物」序曲
- ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲
- ヴァイオリン:ヴィクトリア・ムローヴァ
- シューマン 交響曲第3番「ライン」
- 指揮:ダニエル・ハーディング
- ドイツ・カンマーフィル・ブレーメン
- 東京文化会館
ハーディングという指揮者は夏頃にラジオで知りました。ベルリン・フィルの定期を25才の若さで振ったとかいうもので、ベルク、ブリテン、シューマンという組み合わせでした。その中でもシューマンは、こんなことができるのかというすごいものでした。過去の巨匠が決してなしえなかったことで、演奏が難しいのを曲のせいにし続けたことが見事に否定されたのでした。内声を充実させることで構造を明確にし、逆に厚くなっている旋律線を軽くすることで曲のイメージを一変させてしまいました。
という期待が高まる中、聞きにいってきました。
ドイツ・カンマーフィルはバロックオーケストラだったのか? 編成は7−6−5−4−3。vn1、vc、va、vn2の順でベースはvn1の後ろ。ベースのトップはバロックボウを使っているし、よく見えなかったので確認はできなかったが、その他もバロックを使っている人もいるようだ。もちろんホルン、トランペットはナチュラル。フルートも一人は木を使っていた。
これは以前のユンゲ・ドイチュフィルであり、ハーディングの前任者の音楽監督はバロックヴァイオリンの権威であった、などということがパンフレットに書いてあった。そうなのだ。ドイツはもうこんなに進んでいるのだ。モダンのオーケストラが平気でこんなことをやってしまう。これは器用さの問題ではなく、信念の問題である。
と、序曲で圧倒されていると、ヴァイオリン協奏曲が始まる。どうしてムローヴァなのかな? 客集めなのかな? と考えていたのだが、序曲でわかってしまった。ムローヴァはバロック音楽(特にバッハ)をものすごく研究していて、モダンを使っているのだが非常にバロック的なアプローチをしている。だからこの人たちをまったく違和感がなく演奏できるのだ。単に完璧なテクニックだけではなく、楽器を選んで(いるはず)音色的にも考えられている。協奏曲で指揮者とソリストの考えが一致するなんてことはとても珍しい。全員が納得して、わかっていて音を出すと音楽は魔術になる。
シューマンはラジオのベルリンフィルはさすがにかなりレガートだったが、ここではアーティキュレーションが強調され、輪郭がはっきりしてくる。驚いたことにベースのトップはモダンボウに持ち替えているし、ホルン、トランペット、フルートまでもが持ち替えている。すごい。あれ? ここはキザミだったのじゃなかったっけ? というような部分があったが(記憶不確か)、どこをとっても説得力のある音。
ドイツのオーケストラはここ10年ほどでものすごいレベルにきているのではないか、と感じていました。中でもベルクなど新ウィーン楽派の演奏が確信を持って、あるいは十分に消化されてなされてきているのです。それと同時に古典音楽に対してもものすごいことが起きているのでした。もうすでにモダンだバロックだ、というのは過去の遺物となっているのではないでしょうか? それに引き替え日本の音楽状況は。
2001年10月10日
ジャン・フルネ指揮 新日本フィルハーモニー
- ラヴェル クープランの墓
- ドビュッシー ピアノと管弦楽のための幻想曲
- フランク 交響曲ニ短調
- ピアノ:野原みどり
- 指揮:ジャン・フルネ
- 新日本フィルハーモニー
- オーチャードホール
チケットをいただいて聴いてきました。
ラヴェルはオーケストラがこなし切れていない(理解し切れていない)部分があり、そこそこ。
ドビュッシーはコンチェルトというよりも、オケの中のピアノパートにした方がいいのでは? と思いました。ピアノが主役ではなく、オケが主体。フルネはこの曲を広めたいらしい。
フランクは想像もしなかった演奏。どうしても簡単、単純なイメージがあるが、フルネはまるでブルックナーのような構築をする。曖昧な点はなく、軽やかに気軽にいくのではなく、まず構成があるのだ。演奏時間も長くなるし、気分が休まるときもなくなる。
今日の演奏の評価は下せない。よくわからないのだ。フランクにふさわしい演奏なのか、と言いきれないし、これがフランクなのだよ、と言われれば、はいそうですか、といわざるを得ない。
新日フィルは大健闘。以前よりもオケの質は上がっていると思う。トロンボーンが響きを支えられていなかったか? 不満はホールの響き。
2001年10月9日
ズビン・メータ指揮 バイエルン・シュターツカペレ
- ベートーヴェン 交響曲第9番
- ソプラノ:アマンダ・ルークロフト
- メゾ・ソプラノ:藤村実穂子
- テノール:トーマス・モーザー
- バス:ブリン・ターフェル
- 指揮:ズビン・メータ
- バイエルン・シュターツカペレ
- 東京文化会館
身体が震え、涙が出てくるくらい、ひどい演奏会でした。
もう、第9の精神はドイツ人にしかわからない、とかいう御託は信じないことにしました。アンサンブルはない、音は汚い、弾けていないのに、自分さえ弾ければよい、という最低なオケに成り下がったのでした。
始まった瞬間に「帰ろう」と思いましたが、隣の席にも人がいることだし、とりあえず最後まで聴きましたが、終わった瞬間に椅子を蹴って帰ってきました。
2001年2月27日
ユーリ・バシュメット & モスクワ・ソロイスツ合奏団
- J.S.バッハ(ダンカン・ドルース編) ブランデンブルク協奏曲 第7番
- ショスタコーヴィチ(A.チャイコフスキー編) ヴィオラと弦楽のためのシンフォニア
- モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲
- ヴァイオリン:樫本大進
- 指揮・ヴィオラ:ユーリ・バシュメット
- モスクワ・ソロイスツ合奏団
- 東京文化会館
実はバシュメットは初めてです。樫本大進も初めて。
最初のバッハは? ブランデンの6番を模したものだが、あまりおもしろくなかった。2番のヴィオラの人も相当がんばっていたが、バシュメットが相手だと困っちゃうね。
ショスタコのは弦楽四重奏の第13番を編曲したもの。いろいろな仕掛けがあり、この人たちはこういう曲で力を発揮するのだな。弓で譜面台をたたく、という部分があるのだが、奏者にとってはいやだろうな。ふつうのコル・レーニョとどっちいやだろう。
モーツァルトは最初のfpがなく、あれっと思ったが、へんてこりんなものではなかった。たぶんベーレンラーターだろうが、バシュメットはアーティキレーションを自在に変えているのに対して、大進は清潔な音で譜面に忠実に弾いていく。さすがに一緒のところは統一していたが、ひとりで弾くところは基本的にそれぞれのことをしていた。
バシュメットの表現力はモーツァルトをちょっと超えていた、と思ってしまうが、大進のようにきちんとその枠の中で演奏する、といったものを聴くとどっちがおもしろいかなあ、というところでしょうか。
2000年10月19日
マキシム・ヴェンゲーロフ ヴァイオリン・リサイタル
- モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第40番 変ロ長調 K.454
- シューベルト 幻想曲 ハ長調 D.935 Op.169
- ブラームス ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.108
- クライスラー ウィーン奇想曲・美しきロスマリン・中国の太鼓
- ヴァイオリン:マキシム・ヴェンゲーロフ
- ピアノ:ヴァグ・パピアン
- 東京文化会館
ヴェンゲーロフは、一度、ライプツィヒで聴いたことがある。ブルッフのコンチェルトをやったのだが「ふ〜ん」という感じだった。ところがアンコールにイザイの無伴奏ソナタをやってぶっ飛んだ。ホール全体がぶっ飛んだ、という感じだった。難しければ難しいほど力を出す、というより、うれしくなって弾いてしまう、印象だった。
今回は、超正統派、ストレートにヴァイオリンの名曲を集めたもので、ヴェンゲーロフだったらもっと超絶技巧のものが聴きたいな、と思ったのも確かだ。
最初のモーツァルトはピアノがヴァイオリン以上の比重を持っているのに、ピアニストが今ひとつで、十分楽しめなかった。ヴェンゲーロフもたっぷりとした音で弾くのだが、モーツァルトである、という音楽の痕跡は残らなかった。
次のシューベルトは、非常に安定した技術で、楽しませてくれたが、やはりピアノに不満が残る。フレーズが聞こえてこないのである。長いフレーズの中で、ピアノはいろいろな音を埋めていかなくてはならないが、全ての音が同価で、しかも音が点でとらえられているために、音楽にならない。
ブラームスも骨太の音を聞かせてくれた。どの弦のどの音域でも非常に安定していて、高音域でも耳障りな音にならないので、とても心地よい。
クライスラーは、もうお手の物。これはピアノが完全に伴奏だから一番楽しめた。ただ、どの曲でもそうなのだが、ヴァイオリンがほんのちょっとためようとするときでもピアノがお構いなしに「があ」って出てしまうので興ざめになってしまう。
アンコールはラフマニノフのヴォカリーズとバッツィーニ。バッツィーニは全然難しく聞こえないので、スリルが減った。
ぼくはやはりソロとかにあまり興味がないので、どう弾いているか、というより、どのように音楽をとらえているのか、どんな音楽を聴かせてくれるのか、が気になる。今回のようなプログラムだと、ヴェンゲーロフの妙技だけではなく、ピアニストとのアンサンブルを聴きたいわけである。
2000年9月22日
ミラノ・スカラフィル
- ベルディ レクィエム
- 指揮:リカルド・ムーティ
- NHKホール
これもずいぶんさぼっていました。いくつかとばしてしまいましたが、スカラから書いてみます。
NHKホールという最悪の条件であったが、結果は最上のものとなった。
ベルディのレクィエムなんて普段聴きもしないし、自分とは関係ない曲だと思っていた。合唱の人だったら大事な曲なんだろうなあ、って。しかし、やはり、名演に出会うと名曲であることがはっきりわかる。
なんといっても演奏者全てが何をやるべきかわかっているし、まさにその場面でそれ以外の音はない、と納得させられる連続。唯一気になったのは、ソプラノソロで、音程の不安定さとか、リズムや歌い回しがどうも周りとはまらない。しかし、これも他の演奏だったら気になっただろうか?
改めて音楽とは知的な作業なのだと思う。オーケストラ、しかも合唱が入る大オーケストラで全員が役割を理解するなんてことはたいへんな作業だ。イタリア人がイタリアの名作を演奏する、というだけでは解決できない、もっと高次元での知的作業があるのだ。
我々が日本人の作品を演奏すればそこまでの知的興奮が得られるのか? 残念ながら、肉体的興奮は得られても、まだそれ以上のものはないと思う。それは日本の曲に名作がないから? 演奏者に問題があるから? まあ、いろいろな問題はあると思うが、結局そこまで考えていないんだよね。
しかし、ウィーン・フィルがモーツァルトやシュトラウスを演奏するとき、知的興奮と言うより、確信というか、自信というか、別次元のものを感じる。これは、どちらがいいとか、どちらが上とか言うのではなく、音楽に対するアプローチの違いだと思う。
音量のバランスにしても、指揮者に指示されてするものと、プレーヤー自ら判断して行う(もちろん指揮者は微調整するが)のとでは結果は大きく変わってくる。それが音に現れると思う。音楽を作る作業って、形のないジグソーパズルを組み立てるようなものだ。パズルの形を作っていくのは作曲家であり、指揮者であり、演奏者である。そしてその設計したパズルにピースを当てはめていくのだが、設計したピースと当てはめたピースが全然あっていないこともある(というかその方が多い)。そのピースがぴたりと当てはまるときに知的興奮がわきおる、と思う。
最初にも書いたが、NHKホールであったことが残念だ。上野だったらどんなによかったことか。
2000年2月29日
イスラエル・フィル
- リムスキー=コルサコフ「シェエラザード」
- ショスタコヴィッチ 交響曲第5番
- 指揮:ズビン・メータ
- 東京文化会館
ついにイスラエル・フィルの音を聞くことができました。
ロシア・プログラムなので「ちょっと嫌だなあ」と思っていましたが、なんと美しい音を奏でてくれるのでしょうか。弦楽器の音が美しいのはもちろん、力強く、こんなに大きな音が出るとは思ってもみませんでした。
特にヴァイオリンはセカンドの後ろまで全弓を使い切り、見ていても気持ちのよいものでした。ショスタコの第3楽章の出だしでは、ディヴィジを後ろのプルトだけで始めさせていましたが、とてもしっかりした音ですばらしい実力を感じさせていました。
それに引き替え、ヴィオラはちょっと?でした。ここぞというところで音程の精度が悪いのと、リズムが?な部分がありました。音もぶんぶんいわしていて、ヴァイオリンがとても高級な音色を作っているのと対照的でした。チェロは常にチェロの音色をきかせてやれ、みたいな部分があり、すばらしい音なのですが、もう少し音色を変えてもいいのでは?と思うこともありました。ベースは9人のうち3人がジャーマン・ボウ。とても安定しているのでオケの音程感がゆがむことがありません。すばらしい。
ヴァイオリンは常に美しい音を聞かせ、ここぞというときに出てくるとっておきの音がびっくりするほどすばらしく、涙が出てくるほどでした。しかし、なんの拍子か、アンサンブルが乱れるときがあり、おや、と思うのですが、すぐに元に戻り「冗談、冗談」といっているみたいに何事もなかったように続きます。それにしてもショスタコの最後など弦楽器が刻んでいると、ブラスがかき消されるほどです。これはすごい。
昔、コンクールで優勝した若者がご褒美にイスラエル・フィルでパガニーニを演奏することになり、そのリハーサル中にヴァイオリン全員がソロを弾きだして、若者が泣いてしまった、なんていう話がほんとに信じられます。
管楽器は弦楽器に比べると安定度に欠けますが、ホルン4本がハープと同時に鳴るところなど、オルガンが鳴ったのか、と思うほどでした。ティンパニは弱音のロールなどスネア・ロールをしていて面白かった。
アンコールはムソルグスキー「ホヴァンシチナ」、チャイコ「白鳥湖のワルツ」、プロコ「ロメジュリ」の一番難しいやつと、大盤振る舞いでした。メータは安定しているけれど、これといって何もせず、オケにほとんど任せきっているようでした。時折危ういヴィオラにキューを出したりしていましたが。
というわけで、久しぶりに満足した演奏会で、幸せな気分で帰ってきました。
1999年10月28日
ベルリン・ドイツ交響楽団
- マーラー 交響曲第3番
- 指揮:ケント・ナガノ
- アルト:ダグマル・ペツコヴァ
- 合唱:りつゆう会合唱団
- 児童合唱:TOKYO FM少年合唱団
- 東京文化会館
都民劇場の会場が文化会館に戻り、ぼくとしては初めての演奏会。壁にペンキが塗られただけのようなきもするが、よく見ると、ステージの板も張り替えられているようだ。
久しぶりに聴く、ドイツらしい響き。というか、上野のホールの響きがうれしかった。直接音がすべて聞こえてくる、というのはやっぱりうれしい。
マーラー自体はぼくは好きなのかどうか、まだわからない。オケは優秀。アルトは曲に合わなかったか。低音域が苦しい。合唱はよい。少年合唱はどうやって音をとっているのでしょう?
1999年9月3日
サイトウ・キネン・フェスティバル
- ベルリオーズ 「ファウストの栲罰」
- 指揮:小澤征爾
- 長野文化センター
不安と期待の入り交じったサイトウ・キネンです。小澤=サイトウ・キネンでベルリオーズとくれば絶対に間違いのないものですが、オケがどういう音を聞かせてくれるのか、楽しみです。
予想外にオケはおとなしいものでした。常にきれいな音を聴かせてくれました。うたはテナーを始め、大変に立派なものでした。女声はソプラノにしてはくすんでいてなんかコントラルトみたいだなあ、と思っていたらメッツォでした。どの声域も無理なくでていてすばらしいものでした。
合唱は声はよく出ていましたが、少しがなるのと音程が正確でないのが気になりました。
それに比べ、オケの方はあっさりしていました。なんなんでしょう。声の方には確かに聞こえます。ヨーロッパのオケにもまま聞こえることがありますが、充実した響きの中にノイズというか、歪みというか、音そのものでないものが感じられます。それがサイトウ・キネンのオケからは聞こえてこない。なんと言ったらよいのだろう。そう、まるでCDを聴いているような感じだ。これは日本のオケでよく感じる部分だ。ただ単に、よい音程、よいリズム、よい音色で演奏していればそれでいいのか? 本当に充実した響き、ホール自体が鳴っている感覚、その他技術では解決できない問題。
このあたりはよくわからないので、継続検討課題とします。
1999年6月11日
チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団
- オネゲル パシフィック231
- メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
- 独奏:竹澤恭子
- ベートーヴェン 交響曲第7番
- 指揮:デイヴィッド・ジンマン
- 東京芸術劇場
ベートーヴェンの新全集(?)で演奏するというふれこみで、期待が高まる。オケも指揮者もお初です。
パシフィック231は楽しい曲ですが、積極的に聴こうとは思わない曲なので、こんな機会はありがたいです。演奏は少し荒いですが、なかなか聴き映えがしました。
メンコンは出だしのオケとソロのテンポが違ったりと違和感がありました。そもそもオケはドライな体質であるらしいのに対し、竹澤さんは少し重たくやりたいみたい。メンコンなんて今時難しいよね。結局、ほとんど寝てしまいましたが、メンデルスゾーンについてはそのうち勉強してみようと思っています。
さて、休憩後のベートーヴェンはどう聴かせてくれるのか楽しみです。序奏からして、ピリオド奏法をふんだんに取り入れ、前半とは全く別のオーケストラのようです。ヴァイオリンのテーマはオールダウンで弾いていましたが、2ndヴァイオリンの方が揃っていました。1stはアインザッツも音の長さも揃っていなくて「どうして?」でした。
さて、Vivaceに入ってフルートがきちんと吹けていないのでありゃりゃ、と思っていると、テュッティになると「何だこりゃ!!!」ベト7は1にリズム、2にリズム、3、4もリズム、5もリズム、というくらいリズムに最大の注意を払ってほしいのですが、実際僕はまともに演奏されたベト7を聴いたことがない。8分の6拍子を実現するときっと踊り出すようなリズムになると思うのですが、テンポを早くすると4分の2拍子に近づいてきて、今回はほぼ完全な4分の2拍子でした。以前、フランクフルトだったかシュトゥットガルトだったかを聴いたときも「もうドイツ人でもこのリズムは実現できないのかあ」とがっかりしましたが、このリズムの演奏の仕方は変わってしまったのでしょうか? 世界的に何か決まりでもできたのでしょうか?
表面的にピリオド奏法を取り入れたり、新全集(どこが違うのかわからない)で演奏するのもいいですけど、基本的な、一番大切なところをまともにやってくれないと聴く気がしない。ピリオド奏法をまじめに取り入れている団体の多くはもっと真剣に音程やリズムを注意深く研究していると思う。テンポが速いとか、人数が多いとかという問題もあるだろうが、そう簡単に理想的な演奏はできない。
第2楽章はほとんどアタッカで始まった。木管の和音はブリッジである、という解釈か。第3楽章は完全にリピートしている。そういえば第1楽章もリピートしていたな。トリオも速いテンポのまま演奏されるが、これはすでに目新しくない。
第4楽章はテンポが安定せず(ただでさえ難しいことなのに)、いらいらさせられる。アクセントの位置が違って聞こえたが、これは新解釈というより、単に技量の問題、あるいは無関心のせいだろう。
終わった瞬間に席を立ってしまった。通路から奥まった席で、多くの人の前を通り抜けなければならなかったが、おかげで早く帰ることができた。
1999年5月6日
ゲヴァントハウス管弦楽団
- R.シュトラウス 「ツァラトゥストラはかく語りき」
- ブラームス 交響曲第4番
- 指揮:ヘルベルト・ブロムシュテット
- 東京芸術劇場
九州演奏旅行の直後、眠い目をこすりながら池袋着。ゲヴァントハウスは僕が生まれて初めて聴いた外国のオーケストラで、93年の新響ベルリンツアーの際に寄ったライプツィヒでの演奏会に次いで今回が3度目の体験だ。
オケの配置は下手から1.Vn、Celloその後ろにBassVla、2.Vnという昔のスタイル。チューニングが始まると思わずうれしくなってきた。弦楽器の音色が倍音が多く、僕の好みだからだ。オルガンのピッチに合わせていたけれど、その場その場で合わせていくのかねえ、大したもんだ。
「ツァラ」が始まる。バランスがよくない。3階席だとだめなのかなあ。具体的には弦楽器、特にヴァイオリンが聞こえにくい。冒頭部分はブラスバンドでは決して表現できない、弦楽器の音色がとても重要だと思うのだが、物足りなかった。チューニングの時の印象とはちょっと違うようだ。ヴィオラのソロは太い音で始まり、外側のおじさんが弾いているのかと思ったら内側のお姉さんで、なかなかよかった。ただ、フレーズが弓の返しで切れてしまうのが惜しい。
池袋のオルガンって、あまりいい音を聴いたことがないんだが、なんかぼーっとした音だよね。きらびやかさがない感じ。
演奏は全く破綻がなく、安心して聴いていられるのだが、おもしろくないなあ。ゲヴァントハウスを聴いたっていう感覚がない。ゲヴァントハウスの特徴って何? と聞かれてもよくわからないのですが、こういう演奏だったらどこのオケでもいい、と思いました。うまいだけのオーケストラは世界中にたくさんあるもんね。コンマスのソロは安定していなくて×。
休憩後はブラ4。出だしのチェロとヴィオラのアンサンブルが悪く、つながらない。だんだんおもしろくなくなってきて眠くなる。ゲヴァントハウスって世界最古のオーケストラだとか何とかいっているけれど、おもしろくないんじゃ意味がない。
セカンドヴァイオリンの後ろの方に、おそらく93年にライプツィヒで見たときにもいた張り切りお兄ちゃんが弾いていて、周りから浮いているのだが、演奏する姿勢は背筋が伸びていて一番良かったんじゃないかな。
1999年1月28日
ベルリン・フィルハーモニー・バロック・ゾリステン
- アルビノーニ 5声のシンフォニアト短調
- タルティーニ チェロ協奏曲ニ長調
- チェロ:ゲオルグ・ファウスト
- シュターミッツ ヴァイオリンとヴィオラの協奏交響曲ニ長調
- ヴァイオリン:ライナー・クスマウル
- ヴィオラ:ヴォルフラム・クリスト
- J.S.バッハ ヴァイオリン協奏曲イ短調&ホ長調
- ヴァイオリン:ライナー・クスマウル
- J.S.バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲
- ヴァイオリン:ライナー・クスマウル
- ヴァイオリン:ライナー・ゾンネ
- 東京芸術劇場
ベルリンの人たちがモダンの楽器を使ってバロックを弾く、という目論見だが、バロックの奏法をかなり取り入れ、昔のモダンバロックとは全く違うアプローチである。ヴィヴラートのかけ方を変え、メッサ・ディ・ヴォーチェ(もどき)を取り入れここ10年ほどで世界的にバロック観が変わったことを感じさせる。ただ、トリルだけはモダン風で違和感があった。いつでも同じように最初から早くかけていると工夫がないなあ、と感じてしまう。
だが、1曲目のアルビノーニが鳴った瞬間にがっかりした。音程が悪いのである。特にバスがひどいが、ヴァイオリンも合っていない。チェロ・バスは音程の取り方が全く違う。どうして合わせようとしないのか。半音の取り方が全く違い、ひどいときには4分音くらい違う。音程の問題は最後まで続いたが、合わないことのほかにひとつ気がついたことがある。全体的に音程の取り方が平均率である。つまり、旋律にメリハリがなく、ハーモニーが完全には合っていない。ベルリンって昔から「音の厚みって音程の厚みじゃん」と思っていたけれど、今に至るまでそうなのか?
タルティーニのチェロ協奏曲はファウストが安定した演奏を聴かせるが、聞いているうちに音色に飽きがくる。もっといろんな音を出してくれると楽しめるのに。このあたりがモダンの限界か?
シュターミッツではヴィオラのクリストに感動。その技巧もさることながら、音色がすばらしい。クリストはソロだけでなく、バックに回っても圧倒的な存在感がある。それとあのノリの良さ。クスマウルと掛け合いですばらしいコンチェルタンテを見せてくれた。クスマウルは確かに安定しているし、音もよいのだが、地味で、特にクリストとの対比では少し音が硬いかな。
後半はバッハのヴァイオリン協奏曲全曲。2番の終楽章、最後のところでクスマウルがヒヤッとさせたが、全体に安定していた。クスマウルはソロの時は真正面を向くのだが、アルビノーニとタルティーニではほとんど客席に背中を見せていたのがおもしろい。
ドッペルコンチェルトではクスマウルのストラドがゾンネの楽器(明記されていない)を圧倒して、バランスが悪かった。表現もそれぞれで、打ち合わせもなしでやっているのか? と思ってしまった。
かなりまじめにバロックに取り組んでいるし、アーノンクール達のおかげか研究も進んでいるようだが、音程と音色の問題は是非とも解決してもらいたいものである。モダンの楽器だからといって、微妙な音色が出せないはずがない。テンポはごくまっとうなもの。バロックの成果をきちんと取り入れているのだが、それ以上のものはなく、魅力に欠ける。それが証拠にかなりの客がうなだれていた。後ろのオヤジはいびきまでかいていた。もっともなれない人にあれだけバロックを聴かせればだれだって眠くなるか。僕自身はちょっと寝不足だったのだが、意外にも最後まで寝なかった。これがマーラーだと確実に爆睡していただろう。
アンコールにヴィヴァルディの「四季」から2曲、秋の第3楽章と冬の第2楽章。ヴァイオリンのピチカートは最高。これがベルリン・フィルだ。クリストは単音ののばしで最高の表現をしていた。
1998年12月9日
キーロフ歌劇場管弦楽団
- チャイコフスキー ロココヴァリエーション
- チェロ:マリオ・ブルネロ
- マーラー 交響曲第6番
- 指揮:ワレリー・ゲルギエフ
- 東京芸術劇場
今日は池袋に着いたのがぎりぎりで、客席に息を切らせて駆け込んだ。3階の最後列。右隣が空いていたのでラッキー。いつものように曲目を把握していないので、プログラムをもらってから「ロココとマラ6かぁ、長いなあ」とため息をつく。
ロココが始まり、なかなか良い音しているな、と思う。精密なアンサンブルではないにしろ、ロシアのオケにしては上品な音だ。チェロが入る。今ひとつヌケが悪い音だが、張り切って弾いている。最初は良かったのだが、聞いているうちに無理矢理出している音色が嫌になってきた。アタックの音が3階の最後列まで聞こえてくる。もっと力の抜けた、広がりのある音が僕の趣味だ。ま、楽器の問題もあるから、難しいけどね。オケは12−10−8−8−4型で、こちらの音はなかなか好感が持てたが、何しろ曲がつまらない。それから、ソロは音程が悪い。アンコールでスペイン風の無伴奏曲をやっていたけれど、調がはっきりしない部分もあった。
休憩中は客席で文庫本を読む。
休憩後、マラ6が始まる。開始早々、こりゃ、最近では珍しいきちんとしていないマーラーが聞けそうだぞ、と内心喜ぶ。編成は、17!−14?−12−12−7!。ベースでフレンチボウは2人のみ。リピートしたあとの251小節目で、弦とホルンがバラバラになり、一瞬ひやっとした。これをきっかけにアンサンブルの乱れが目立ち始めた。常にトロンボーンが大きすぎてバランスが悪い。大きすぎるというより、「コーン」という、音楽とは関係のない音だ。
聞き進むにつれ、音色の単調さ、本当の静かさがないことに飽きてきた。特にあんなに長い曲で平板だと拷問だ。お互いに音量を競っているような場面も見られ、ちょっとなあ、と白けてしまう。
以前にロシア国立響(だっけ?)のマーラーを聞いたことがあるが、あれはマーラーなんて何のこっちゃ、という演奏だった。今回はオケもある程度ヨーロッパ風で洗練されているし、技術的にも安心して聞けるが、指揮者のマーラー感もあるのだろうが、やはりしっくりこなかった。別にマーラーに特別な思い入れはないのだが、おもしろい演奏はないかねえ。
|